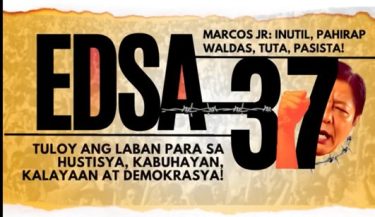ルボン 村のお葬式
大橋成子(ピープルズ・プラン研究所、APLA理事)
私事になるが、先月93歳の母が老衰でこの世を去った。
葬儀の前に遺族が故人と共に過ごす時間は、宗派を超えてどこの国でも同じかもしれないが、お寺での母の静かな通夜のなか、ふと私は、かつてネグロス島で暮らした小さな漁村で体験した、村あげての賑やかな葬儀の風景を思い出した。
― 日本軍から生き延びたペドロ爺さん
パナイ島で生まれ育ったペドロ爺さんは、日本軍の殺戮が激しくなった1944年にネグロス島のナヨン村に親戚を頼って移住したという。当時一日3便の避難船がパナイからネグロスに出ていて、彼が乗りこんだ船が最後の便だったらしい。
「妊婦が日本兵の銃剣で殺されるのを目の前で見た。あの船に乗っていなかったら、きっと自分も殺されていた」と生前、ペドロ爺さんは私に会うたびに戦争中の話しをしてくれた。老衰のため83歳で亡くなるまで、ヒーポン(小エビ)漁では誰にも引けをとらない漁師だった。
― リメジョ・ヒネラルたちの世界
ネグロスには「リメジョ・ヒネラル」という面白い言葉がある。スペイン語がイロンゴ語化したものらしいが、「定職をもたない何でも屋」「日々の稼ぎだけで生きる」人々を指す。社会学者が、いわゆるインフォーマル・セクターという部類に分ける人たちのことだ。大都市の貧困層もそうだが、ナヨン村のような零細な漁村もまさにリメジョ・ヒネラルの世界。
男たちはまだ暗いうちから漁に出て、獲った魚を町まで行商するのは女たちの仕事だ。嵐や不漁で魚が獲れない日は、男たちは大工や修理屋やトライシクル(乗合自転車)の運転手に早変わりし、女たちは、他所の家のラバンデーラ(洗濯女)や家政婦、もしくは家に貯蔵している塩やギナモス(小エビの塩漬け)を売って僅かな日銭を稼ぐ。当たればラッキー、当たらなければ他の手段でサバイバル。実にギャンブラー的な生き方だ。
決して豊かな生活ではないが、女も男も逞しい。村人になにか起こると、我先に駆け付けるおせっかい者たちでもある。昨今日本で問題になっている、老人介護、孤独死、学校でのいじめなどとは、ほとんど無縁の世界だった。
― 「9日間を3回」喪に服す
ペドロ爺さんは、家族や漁師仲間に看取られて自宅で亡くなった。そのニュースは10分もたたないうちに村中に伝わり、そこから、ルボンと呼ばれるフィリピン版の葬儀が慌ただしく始まった。ペドロ爺さんは娘たちが綺麗に化粧をし、白い棺に納められた。棺は1週間ほど自宅に置かれ、親族や住民たちが毎晩慰問に訪れる。そして教会での葬儀ミサの後は、参列者全員で、町にある公営墓地まで行進して納棺を見守る。炎天下でも雨でも、参列者は霊柩車の後について延々と行進するのだ。
日本の仏教式では、葬儀から49日(7週間)後に納骨するのが一般的だが、フィリピンのカトリックでは、納棺後に「9日間を3回」すなわち27日間、遺族宅で法要する。「天国に入るまで、故人を一人にしては可哀そう。残された家族を寂しい思いにしない」と、亡くなった日から1週間、そして葬儀後の27日間、村人たちが夜通し賑やかに振る舞うのだ。これは、遺族にとってはありがたいことでもあり、体力を消耗する大変な時間でもある。
― パナホールとベラシオン
大勢が朝まで一緒に起きていられる秘訣がある。それが、パナホール(賭博)だ。軒先や庭にテントが張られ、何台ものテーブルが持ち込まれ、麻雀やトランプの勝負が徹夜で繰り広げられる。掛け金は5~10ペソと少額だが、遺族の家はその一部を寄付してもらい、眠気覚ましのコーヒーやキャンディを用意する。
パナホールに参加できない子どもたちは、ベラシオンと呼ばれるゲームで盛り上がる。輪になってそれぞれにお菓子の名前をつけて、当てられた子が好きな曲を歌うという他愛のないものだが、このゲームはなぜか葬儀の時しかやらないのだそうだ。バコロド市のような都市ではもう見かけなくなった、村ならではの光景だ。

― 虐殺されたジョニー君
ペドロ爺さんの葬儀は心温まるものだったが、私は、激しい怒りと悲しみに満ちた葬儀にも何度か列席したことがある。そのうちのひとつが、エスペランサ農園で、農地改革を求める労働者たちが農作業中に、地主が雇ったブルーガード(私兵)が突然発砲し、その銃弾にあたって亡くなったジョニー君の葬儀だった。
当時、彼は20代後半で妻は妊娠6か月だった。ジョニー君は労働組合のリーダーだった叔父と間違われて狙い撃ちされたのだ。葬儀には各地の農園から数百人の労働者が集まり、いたたまれない悔しさに全員こぶしをあげて農地改革の実現を約束した。葬儀後に訪れたエスペランサ農園では、ナヨン村と同じように、毎晩親戚や仲間たちが余興を通してジョニー君を弔い、遺族を励ましていた。
ジョニー君の死後、ネグロス島の有力な地主であるベネディクト家と狙撃者に対する裁判闘争が何年も続いたが、検事や裁判官たちへ地主の圧力がかかり、結局うやむやな結末となった。しかし、ジョニー君の死は全国紙でも報道され、国際的な支援も受けたことで、エスペランサ農園の農地改革はようやく実施された。土地登録証を得た元砂糖労働者たちは協働組合を作り、現在も砂糖や野菜を自主生産している。
ネグロス島では、ジョニー君の例に限らず、現在も理不尽な弾圧や殺害は続いている。世論の関心も薄くなるなか、理由もわからず殺された名もなき農民や労働者の魂は、今、私たちに何を語っているのだろうか。せめて天国で安らいで欲しいと願うばかりだが、無残にも命を奪われた故人たちの正義は、残された者が守り続けなければならない。